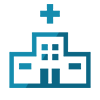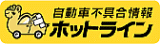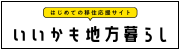医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により一定の限度額を超えた自己負担が高額療養費として支給されます。
町では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により、高額療養費に該当する方を判別して世帯主宛にお知らせ(以下、「お知らせ等」)をお送りしています。
お知らせ等は通常、診療を受けた月から3~4カ月後に届きますので、お手元に届きましたら下記をご持参のうえ、通知発送日から2年以内に住民課窓口にお越しください。
◆高額療養費の支給申請についてのお知らせ等(町からお送りするお知らせ等です)
◆医療機関等の領収書
◆振込口座番号のわかるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)
(ゆうちょ銀行の通帳は振込み用の店名・預金種目・口座番号が必要です)
◆手続きする方の本人確認書類
◆世帯主と高額療養費の対象となった受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
!!高額療養費支給申請手続き簡素化について!!
令和6年5月1日より従来の申請方法を見直し、以下のお手続きにより申請から受給について簡素化を図ることができるようになりました。支給情報を登録いただければ、毎回の来庁手続き(申請書の記載、領収書の提示)が不要となり、高額療養費が発生するとともにご指定の口座に振り込むことが可能となりますのでぜひご活用ください。なお、簡素化を行うためには申請が必要であり、国民健康保険税の滞納がないことが条件となります。
<お手続き>
◆国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書を住民課窓口にて提出
※振込口座は公金受取口座、もしくはご指定の口座を選択できます。
※世帯主の変更、受取口座の変更等があった場合は再度申請書を提出していただく必要があります。
※申請様式はこちら(国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書)
自己負担の限度額
1カ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担合計額が限度額を超えた場合、高額療養費を支給します。
自己負担限度額は以下のとおり年齢や所得に応じて決められています。
※所得区分については、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得などに応じて判定します。
※自己負担割合や自己負担限度額が異なりますので、毎年所得申告が必要となります。
70歳未満の方
|
≪ 自己負担額(月額) ≫ |
||
|
所得区分(注1) |
3回目まで |
4回目以降 |
|
ア.901万円超 |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
|
イ.600万円超901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 |
|
ウ.210万円超600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
|
エ.210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ.住民税非課税世帯(注3) |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計です。
(注2)岐阜県内において過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります(世帯の継続性が認められた世帯に限る)。
(注3)同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
≪同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき≫
同じ世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。医師の処方せんにより調剤薬局で薬の処方を受けた場合は、医療機関と調剤薬局の自己負担額を合算できます。
70歳以上の方
|
≪ 自己負担額(月額) ≫ |
|||
|
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
|
現役並みIII |
課税所得 |
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は |
|
|
現役並みII |
課税所得 |
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は |
|
|
現役並みI |
課税所得 |
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は |
|
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
|
|
低所得者II(注2) |
8,000円 |
24,600円 |
|
|
低所得者I(注3) |
8,000円 |
15,000円 |
|
(注1)岐阜県内において過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります(世帯の継続性が認められた世帯に限る)。
(注2)同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税である方。ただし「低所得者I」の方を除く。
(注3)同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる方(公的年金の控除額は80万円として計算します)。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯で合算する場合は、まず70歳未満と70歳以上の方に分け、70歳以上の方は外来の個人単位で限度額をまとめ(現役並みI、現役並みII、現役並みIIIを除く)、その後外来・入院を合わせて70歳以上の世帯の限度額を計算。
これに70歳未満の方の合算対象額(自己負担額21,000円以上のもの)を合わせて国保世帯全体で適用されます。ただし、後期高齢者医療制度該当者は合算できません。
自己負担額の計算方法
◆診療日の属する暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算。
◆1つの医療機関ごとにそれぞれ別計算。
◆同じ医療機関でも、歯科は別計算。
◆同じ医療機関でも、通院と入院は別計算。
◆保険診療分のみが対象です。(入院時の食事代や部屋代などは計算から除きます)
限度額適用認定証の交付
70歳未満の方、または70歳以上の住民税非課税世帯・現役並みI・現役並みIIの世帯の方が高額な療養を受ける時、国民健康保険資格確認書とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、限度額適用認定証の交付を受けられるのは保険税の滞納がない、または保険税の滞納につき特別な事情がある世帯の方に限ります。
70歳以上の一般または現役並みIIIの世帯の方は国民健康保険資格確認書の提示で、高額な療養を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は不要です。
限度額適用認定証の交付を受けるには、下記をご持参のうえ、住民課窓口(即日交付可)で手続きをしてください。
限度額適用認定証を利用できるのは、申請月の初日以降となります。
◆交付を希望する方の国民健康保険資格確認書
◆手続きする方の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の方がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
◆世帯主と交付を希望する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
なお、有効期限後引き続き限度額適用認定証の発行を希望される方は再度ご申請ください。その際、上記に加えて現在お持ちの限度額適用認定証をご持参ください。
75歳到達月の自己負担限度額
国民健康保険に加入していた方が月の途中で75歳に到達した場合、75歳到達月に限り、国民健康保険と後期高齢者医療制度のそれぞれに自己負担限度額が2分の1となります。(ただし、誕生日が月の初日の方は適用されません。)
岐阜県内の住所異動月における自己負担限度額
平成30年4月1日より、岐阜県内の他市町村へ住所異動した場合の転居月について、転出元の市町村と転出先の市町村における自己負担限度額はそれぞれ本来の2分の1となります。ただし、特定疾病の療養は対象外となります。
75歳到達と県内他市町村への転居が同月に発生した場合は、両方の適用を受ける個人単位で、限度額は本来の4分の1となります。
※上記の取り扱いは、世帯の継続性が認められた世帯のみが対象となります。
マイナ保険証利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)